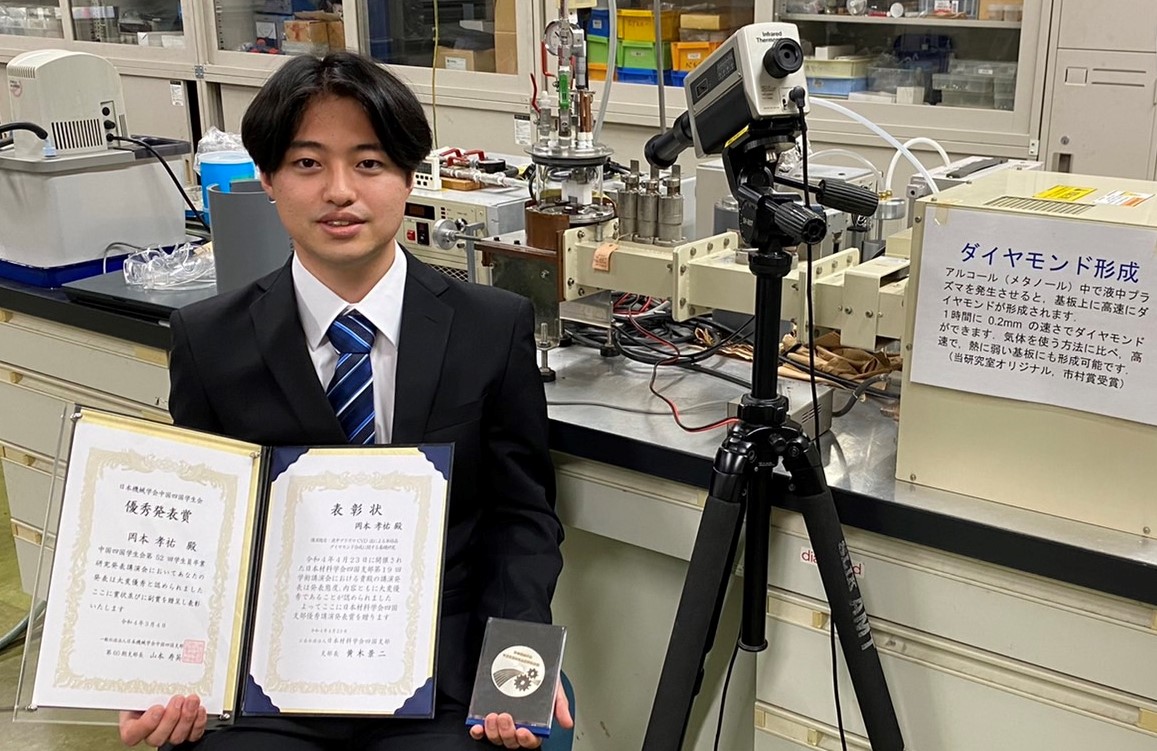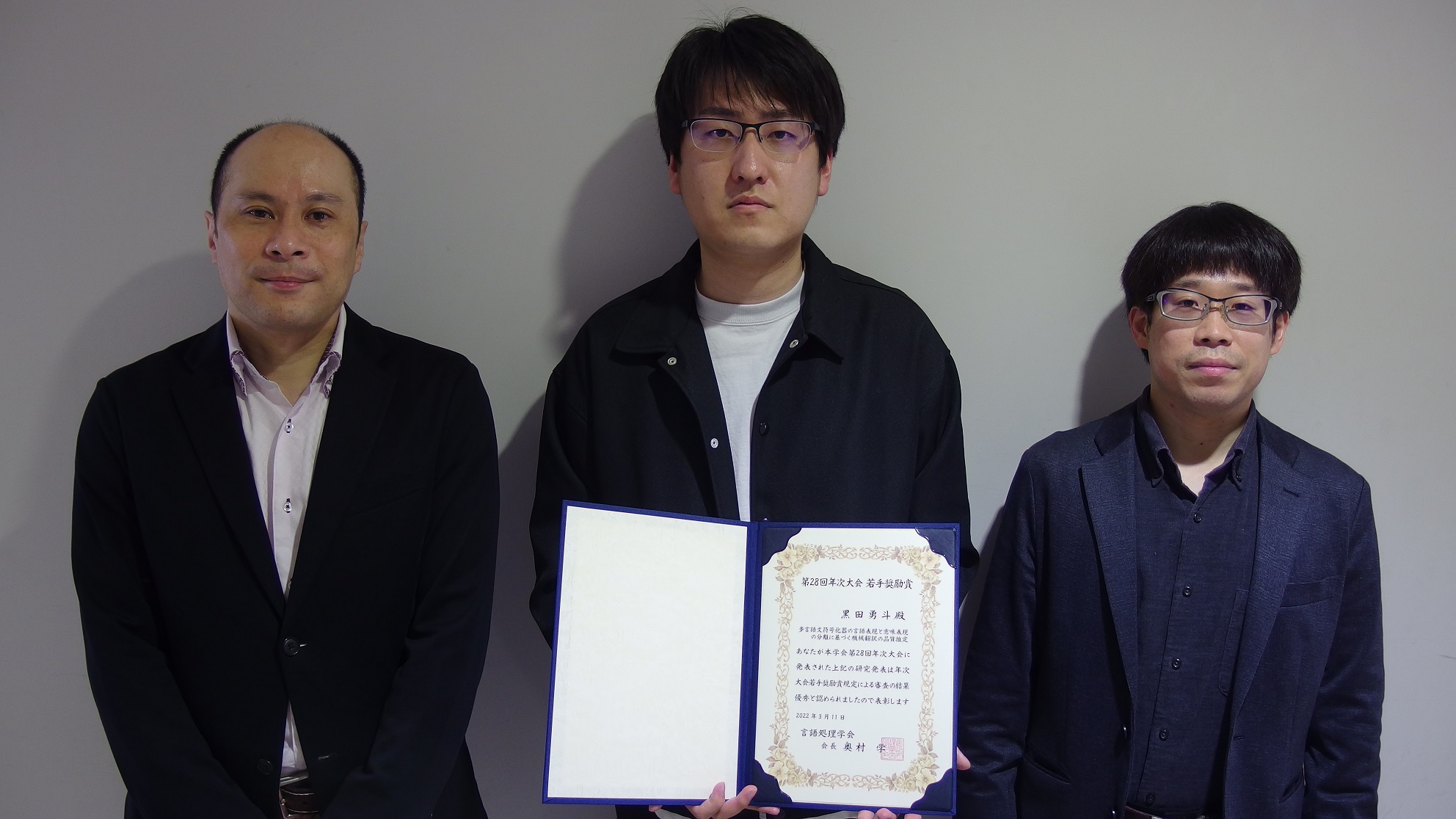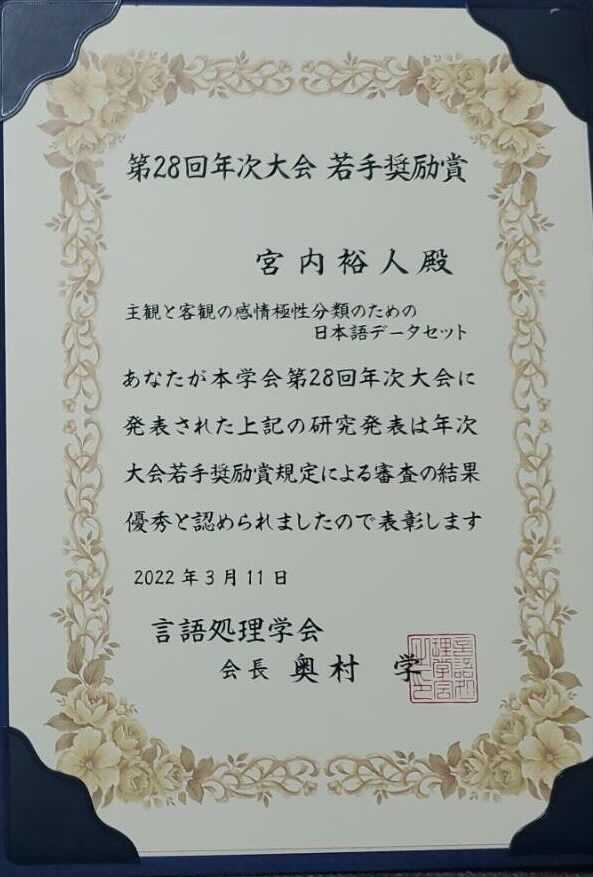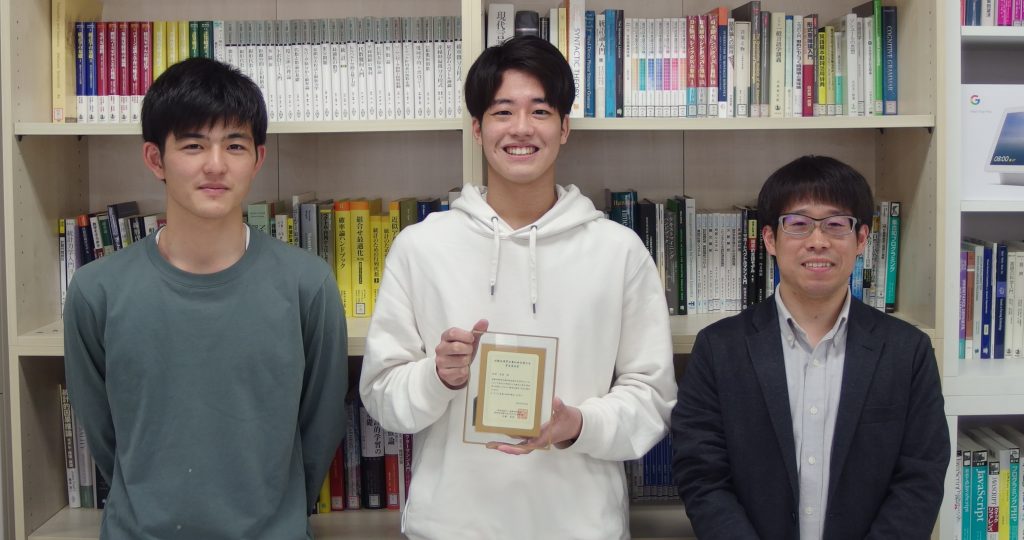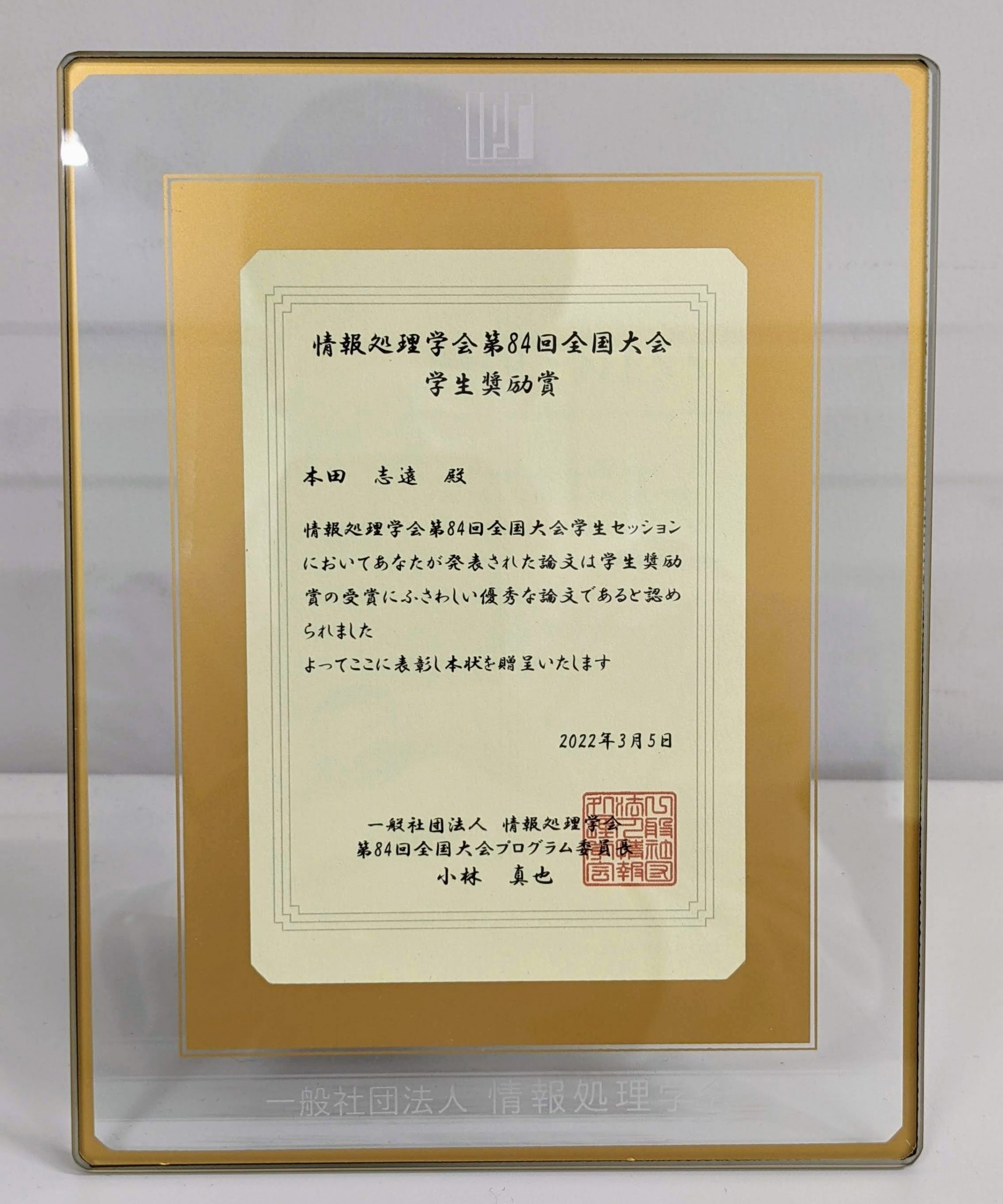今年度のオープンキャンパスは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「愛媛大学Webオープンキャンパス特設サイト」(7月20日(水)公開。下部リンク参照)で行う「Web開催」と、実際に工学部の様々なコンテンツを体験できる「現地開催」(8月10日(水) 要事前申込)の2つの形式で開催します!
現地開催の詳しい企画内容は各コースのプログラム内容(PDFリンク)をご確認ください。
また、工学部独自のコンテンツとして、Web(Zoom)による「入試相談会」(8月9日(火)13:00~)を実施します!(URL:https://zoom.us/j/91458392525)
皆様のご参加をお待ちしてます!
【愛媛大学Webオープンキャンパス特設サイト】(7月20日(水)公開)
URL:https://www.ehime-u.ac.jp/entrance/open-campus/#online
ポスター:https://www.ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/2022/05/oc2022.pdf
【注意事項】
(現地開催について)
※現地開催のオープンキャンパスに参加するには、Webでの事前申込が必要です。
「申込受付(外部リンク)」から、7月13日(水)9:00 から24日(日)24:00の期間内にお申し込みください。
事前申込をしていない方は参加できませんので、ご注意ください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大や自然災害の発生等により、中止となる場合があります。その場合は愛媛大学ホームページでお知らせします。
※今年度の現地開催オープンキャンパスは、高校3年生と既卒者を対象としています。
※秋には、事前申込制(人数制限有)でどなたでも参加できるミニオープンキャンパスを開催予定です。
申込方法については、改めてお知らせいたしますので、ホームページをご確認ください。
(工学部独自コンテンツ「入試相談会」について)
※入室する際は、名前を学校名(漢字)と苗字(カタカナ)で入力してください。(例:愛媛高校イトウ)
※入室時はマイクとカメラをOFFにしてください。
※発言する際は手を上げるアクションを行ってください。ミュートを解除します。
※参加中はホストの指示に従ってください。
※以上の注意事項に違反した場合には、入室拒否及び退出させられることがございます。ご了承の上、ご参加ください。